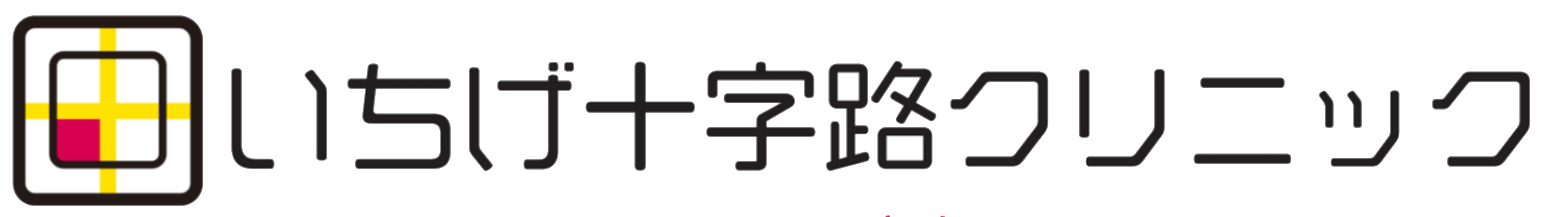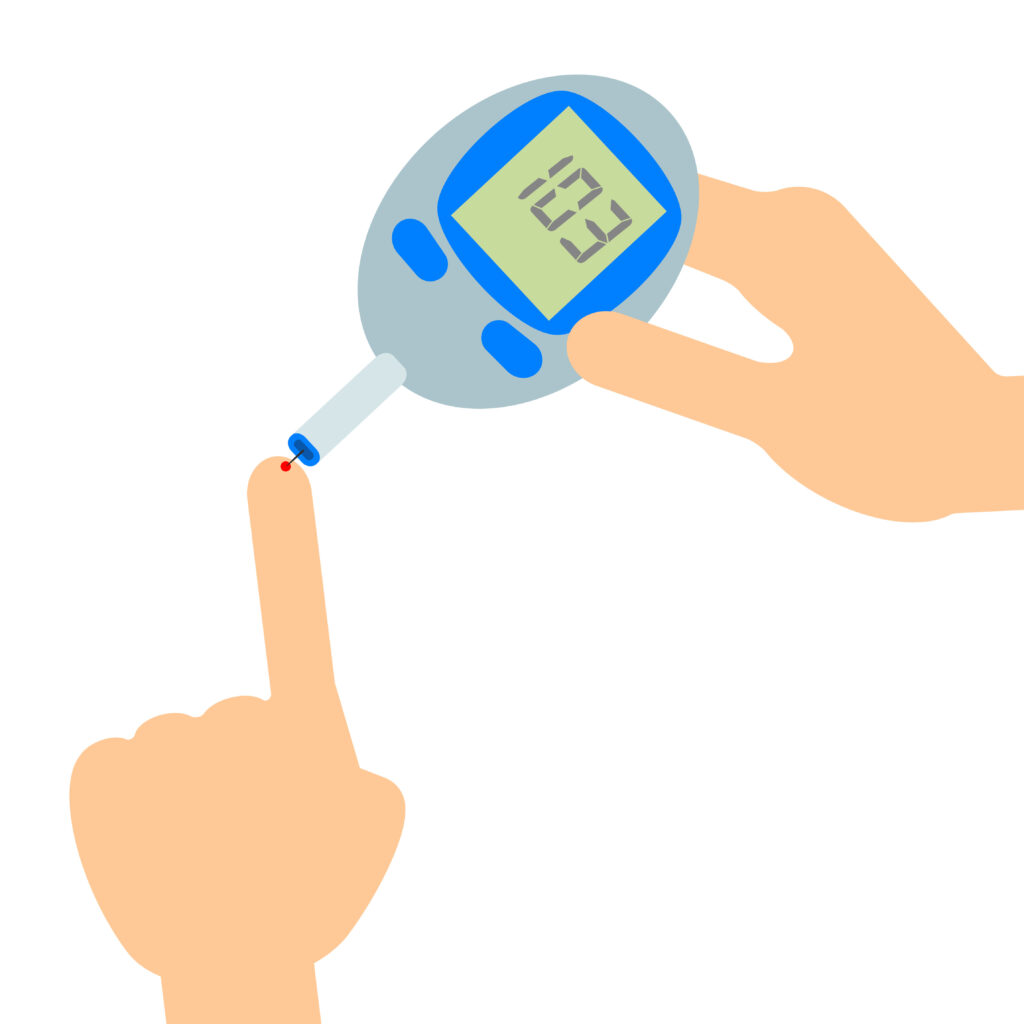糖尿病とは
糖尿病とはインスリン(膵臓で作られる糖利用に必要なタンパク)作用不足による慢性の高血糖状態を主な症状とする代謝性疾患です。
糖尿病は、①1型(インスリンの絶対的欠乏)、②2型(インスリンの相対的欠乏)、③その他(遺伝や病気等で起こるもの)、④妊娠糖尿病に分類されます。
糖尿病になると、口渇、多飲、多尿、体重減少、易疲労感などの特徴的な症状が出現しますが、自覚症状を伴わないこともあります。
また、高血糖状態が続くと網膜症、腎症、神経障害(糖尿病細小血管合併症)や、全身の動脈硬化症(虚血性心疾患、脳血管障害、末梢動脈疾患)を悪化させ、結果的に生活の質が著しく低下することになります。
当院では、糖尿病治療のガイドラインに従い、患者様にふさわしい治療が選択されるよう努めています。糖尿病と診断された方、糖尿病の疑いがある方、糖尿病が心配な方は、お問合せください。
糖尿病の治療
外来診療で治療する場合、最も重視すべき指標はHbA1cになります。HbA1cは、過去1-2カ月間の平均血糖値を反映するものです。
血糖コントロール目標(65歳以上は別途規定)
血糖正常化を目指す際の目標:HbA1c 6.0未満
合併症予防のための目標:HbA1c 7.0未満
治療強化が困難な際の目標:HbA1c 8.0未満
合併症予防のための目標:HbA1c 7.0未満
治療強化が困難な際の目標:HbA1c 8.0未満
その他のコントロール目標
血圧:130/80mmHg未満
血清脂質:LDL 120未満 HDL 40以上 TG 150未満 Non-HDL 150mg/dL未満
目標BMI:[身長(m)]²× 22-25(目標BMI)
血清脂質:LDL 120未満 HDL 40以上 TG 150未満 Non-HDL 150mg/dL未満
目標BMI:[身長(m)]²× 22-25(目標BMI)

食事療法

運動療法
(注)基礎疾患等への配慮(メディカルチェックの必要性)
歩行時間↑などで開始し、以後は継続性が重要

薬物療法
糖尿病は、①インスリン非依存状態と②インスリン依存状態に大別されます。それぞれに対する治療方針をお示しします。
外来診療では、患者様の状態に合わせて薬物療法が選択されることになります。また、インスリン療法の適応が認められる場合、インスリン注射を使用することがあります。